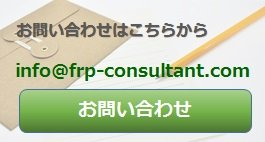JEC World 2025概要とInnovation Award Finalistから見る近年の技術動向
2025年3月4日から6日の期間で開催が予定されている JEC World 2025。
私はここしばらくJECに行っていませんが、
今年は当社の顧問先の方の一部は訪問をすると聞いています。
COVID-19が落ち着いて、大変な円安水準であるものの、
ようやく日本企業からも欧州に行こう、
という流れが出てきたといえるのかもしれません。
今回はJEC World 2025概要とInnovation Award Finalistについて述べたいと思います。
JEC World 2025の概要
Image was referred from JEC Events
JEC World は言わずと知れた世界最大の複合材料の展示会で、例年フランスで開催されます。
場所はシャルル・ド・ゴール国際空港から近い、
パリ・ノール ・ヴィルパント見本市会場(Parc des Expositions de Villepinte)です。
FRPの展示会という方もいますが、
基本的にはFRPを主としながらも複合材料の展示会であることには注意が必要です。
複合材料の展示会である以上、FRPにこだわる必要はありません。
ただ、実情としてその多くがFRP関係の出展となっています。
JEC World 2024の実績
1年前の同展示会の実績によると、
以下のような規模のイメージです。
- 入場者数:43500人以上
- 展示:1300以上
- 出展/参加国: 100以上
業界によっては大したサイズではないと映るかもしれませんが、
複合材料業界に限ってでいうと他にこれ以上大きな展示会は有りません。
JEC World 2025が注目するカテゴリー
以下の14カテゴリーになります。
- Automotive & Road Transportation
- Aerospace
- Building & Civil Engineering
- Defence, Security & Ballistics
- Design, Furniture and Home
- Electrical, Electronics, Telecoms & Apliances
- Equipment & Machinery
- Maritime Transportation & Ship building
- Medical & Prosthetics
- Oil & Gas
- Pipe, Tanks, Water Treatment & Sewage
- Railway Vehicles & Infrastructure
- Renewable Energy
- Sports, Leisure & Recreation
まさに、FRPはもちろん、複合材料が活用されている産業を幅広く、
かつ適切に分類していると感じます。
特に興味をひかれたのが”Pipe, Tanks, Water Treatment & Sewage”の設定です。
高圧水素タンクもそうですが、
インフラ関係の関心の高まりがその背景にあると考えます。
後述しますが、この辺りの動きが従来の炭素繊維ではなく、
ガラス繊維に関する展示、発表内容が当該展示会で増えた一因と考えています。
材料から成形加工、検査、最終製品まで様々なプレーヤが揃っている
これは実際に参加された方も同じ印象を持っているかもしれませんが、
川上、川中、川下に属する様々な企業が多く出展しています。
そのため、知りたい、話をしたい領域がある程度明確化できていれば、
何かしらニーズに合致した企業を見つけることができるでしょう。
設計に関する情報は限りなく少ないのが大きな課題
一方で課題もあります。
JECに出展、参加した経験から言えることは、
圧倒的に設計に関する出展や情報が少ないことです。
これは業界としての共通課題でもあります。
設計に関する知見が少ないために、
今でも形を作るところだけに注力し、
どのような材料、工程、検査について方法を選定するのか、
という議論が出てきにくいのです。
材料と一言で言っても強化繊維の構成や積層構成、
そしてVfやマトリックス樹脂との組み合わせで、
その材料特性も全くの別物になります。
工程についてもどのような温度、圧力、
そしてそれらのプロファイルを適用するかによっても異なるのです。
この辺りを最適化するためには、
全体を俯瞰してみることのできる設計の概念が不可欠です。
設計に基づいた技術要件の明確化、すなわち図面化が終わった後で、
材料、工程、検査、品質保証などの”部品”を組み合わせていくのが開発の定石なのです。
しかし今でも分業の文化が国内外問わず残っているため、
狭い範囲しか技術的議論ができない企業、そして人がほとんどです。
これでは、設計、材料、成形加工、品質保証のつながりの強いFRPは使いこなせないでしょう。
課題解決への道のりはまだ遠いです。
話を JEC World 2025 に戻し、Innovation Award Finalistについてご紹介したいと思います。
Innovation Awardは複合材料業界の技術動向を反映しやすい
JEC World 2025では複合材料業界の技術動向を反映した Innovation Award というイベントを行っています。
JEC World 2025 Innovation Awardsという専用ページがあります。
複数の企業が応募し、審査のうえで Finalist が選ばれ、
さらにその中で受賞企業が決まるという仕組みです。
受賞企業は別の機会にご紹介するとして、
今回はFinalistにスポットを当て、
テーマの概要から見える近年の技術動向と、
適宜抜粋の上でテーマの概要と関連情報をご紹介したいと思います。
Innobation Award Finalist から見える技術動向
これはかなり明確な傾向と理解しましたが、
キーワードは以下の2点です。
- 熱可塑性樹脂
- ガラス繊維
それぞれについて私見を述べます。
熱可塑性樹脂が注目されるのはリサイクル性、環境性、靭性の3点
熱可塑性樹脂に関連したテーマが多かった理由は3点あると考えています。
それが、リサイクル性、環境性、靭性です。
リサイクル性について
リサイクル性は熱可塑性樹脂の温度変化による、
固化と軟化(溶融)が可逆的であるため、
使用済みの材料を熱をかけて再成形できることが大きく貢献しています。
環境性について
環境性についてもその意味を述べます。
熱硬化性樹脂の場合、成形を行う際に熱や光といったエネルギーを供給することで、
高分子化する、つまり重合反応が生じます。
熱をかけて形態が変化するということは、
材料は”重合前”で活性基を有する化学物質であることを意味しています。
活性な化学物質は通常分子量の低いモノマーやオリゴマーであり、
安定な高分子状態の樹脂と比べ毒性が高い、揮発しやすいといった特徴があります。
これに比べ熱可塑性樹脂は材料メーカから出荷の段階で重合反応は終わっており、
熱をかけて起こる変化は相転移でしかありません。
このように熱可塑性樹脂は化学的に安定しているという意味で、
環境性能が高いといえます。
欧州ということもあるかもしれませんが、
熱可塑性樹脂に関するテーマが多かった印象です。
靭性について
最後は靭性です。
粘り強さと言い換えてもいいでしょう。
高分子の粘弾性特性の粘性項の特性を意味しており、
架橋点を持たない熱可塑性樹脂は衝撃等の外的変形を受けた際、
構成する分子の絡み合いがほどけるといった形態変化を起こします。
この変化が比較的ゆっくりであるため、
変形によるエネルギーを熱として放出することが可能となります。
これこそが材料の粘りであり、
トランスバースクラックや層間破壊の発生の抑制につながります。
ガラス繊維の強みは圧倒的な生産キャパシティーによる調達安定性
ガラス繊維の強みはその圧倒的な生産量にあります。
炭素繊維と比べるとはるかに大量に作られているため、
例えばインフラのFRPによる補修など、相応量を使う必要がある際にメリットがあります。
まとまった量を調達することが可能だからです。
弾性率は一般のEガラスで70GPa超、
特性の高いSガラスでも85GPa程度と、
高強度タイプ、並びに中弾性タイプの炭素繊維と比べて1/3以下です。
しかし強度については、
Sガラスであれば室温での引張強度は4500MPaを超え、
高強度タイプであるT700等の炭素繊維の90%数値に匹敵します。
よって、構造部材として高い剛性を求めないのであれば、
ガラス繊維で十分な場合もあるのです。
常にFRPの世界ではガラス繊維が主役でしたが、
それがより分かりやすい形で今後目の前に出てくると想像します。
Finalistの概要
ここから抜粋したFinalistについて、
それぞれテーマ名と概要を述べます。
Thermoplastic Composite Exit Guide Vane / Competence Center CHASE GmbH (AUSTRIA)
スーパーエンプラであるPEEKをマトリックスとした、
CFRTPの静翼に関する話です。
航空機エンジンの部品と考えます。
技術そのものは真新しいものではありませんが、
積層と含浸を同時に進行させるという工程にポイントがあるようです。
実際に使う場合、CFRTPだけではなく先端に金属のプロテクターを使う、
表層に保護層を適用するなどしないと、
エロージョンが起こり部品としては成立しないでしょう。
Induction Welded Thermoplastic Torsion Box / DAHER (FRANCE)
PPSを強化繊維に、低粘度のPAEKをマトリックスとしたシートを、
AFP(ファイバープレースメント)でコーティングすることで、
空力面の段差をなくすという技術が主のようです。
PAEKについては以下のようなコラムでも取り上げました。
※関連コラム
Xencor(TM) HPPA LGF Steering Gearbox Outboard Housing / Syensqo (BELGIUM)
Volvoの販売する電気自動車EX90のSteering Gearboxの成形に、
長繊維のガラス繊維をペレット化したLFTの射出成型を適用したという技術です。
耐腐食性と軽量化が狙いと書かれています。
LFTについては、過去にもご紹介したことがあります。
※関連コラム
UV Pultrusion for manufacturing GFRP Links / German institutes of textile and fiber research Denkendorf (GERMANY)
引き抜き成型ですが、成型時のエネルギーを従来の熱ではなく光にしたというのがポイントです。
一般的に光硬化の硬化物は材料特性が低いと言われていますが、
どの程度の数値を示すのか興味があります。
※関連コラム
Stuttgart大学でUV硬化FRPの研究プロジェクト開始
Glass Fibre Composite Coastal Flood Gate / Infra Composites B.V. (NETHERLANDS)
GFRPの耐水性、耐腐食性を活かした止水扉です。
日本でも材料の寿命を考慮し、これからさらに増えていくかもしれません。
※関連コラム
Paradis bridge, 43m all composite trusswork bridge / FiReCo (NORWAY)
FRPの軽量性と耐腐食性を活かした輸送と設置が楽な橋です。
日本においても、橋は劣化が顕著になると考えられるインフラの一つといえるため、
FRPの適用が期待される領域であると考えます。
※関連コラム
A350 production scrap into MFFD rod / herone GmbH (GERMANY)
A350の機体に使用されている熱可塑性材料であるCFRTP部品の廃棄物を、
ロッドとして再利用するという取り組みです。
当該部品については過去にご紹介したことがあります。
※関連コラム
A350の一次構造材に適用された 熱可塑性CFRP (CRRTP)とその概況
POLAB VALDUR Thermoset Composite Lighting / Professional Lighting POLAB (SWEDEN)
こちらは熱硬化性のFRPを街灯の構造材に用いたというテーマです。
耐腐食性が狙いであり、近年、日本でも起こっている、
街灯の倒壊を回避するアプローチにも応用できると考えます。
※関連情報
SoundPlank / COMPOSYST GmbH (GERMANY)
炭素繊維と木材を組み合わせ、
複合材料としての異方性を活用した音響設備です。
FRPが示す異方性による振動特性を活用した事例で、
過去にはFRP製の楽器をご紹介しました。
※関連コラム
CFRPが適用された アコースティックギター LAVA ME PRO
CrossTrack Composites Manufacturing Software Suite / JETCAM International s.a.r.l. (MONACO)
材料を無駄なく使うためのカットパターンとその積層位置を提案するソフトです。
廃棄物を減らすという意味で、
これもリサイクル活動の一つとして定義されています。
Enhancing Cured Laminate Compensation with AI / Magestic Technologies (USA)
AIで過去の製造履歴から工程を最適化支援するというソフトです。
この手のソフトは増えていくものと予想しますが、
個人的には製造プロセスよりも過去にもご紹介したようなモデリングの方が、
AIとの相性がいいものと考えます。
理由としてはFRPの構成材料の一つである樹脂が、
品質変動幅の大きい高分子であることに由来します。
入口である材料特性のばらつきが後工程に及ぼす影響が大変大きいため、
これは数値化だけでは管理しきれないことに加え、
逆に材料に合わせて工程を変えているようでは、
成型物の品質が安定しないのです。
設計段階で、製品仕様の明確化と材料の振れ幅を許容した公差設定が肝となります。
そのうえで、成形プロセスの温度や圧力のプロファイルは固定する方が、
量産品質安定では望ましいと考えます。
※関連コラム
New Certification Approach for Patch Repair / Bureau Veritas (FRANCE)
FRPによる補修工程の妥当性評価に関する内容です。
破壊靭性特性を重要視しています。
補修材としてのFRP適用は、
これから必ず注目度が高まると考えています。
先進国各国で進行するインフラや工場設備の老朽化が、
その背景にあります。
※関連コラム
FRP製電柱の拡大と既設電柱のFRPによる補修・補強の重要性
建築物のFRPによる補修後の検査方法に関する新しい規格 ASTM WK74694
DTM Wind Blade Tooling by 6m Wide 3D Printing / University of Maine (USA)
巨大な3D printingを使って、風力発電ブレードの製造部品に応用するという技術です。
スケールの大きさは以下のような動画を見るとわかりやすいかもしれません。
Cockpit – handlebar / ENGEL Austria GmbH (AUSTRIA)
GF/PA6のガス射出成型と、局所的にUDのCFRPを適用することでたわみ変形を抑制した、
自転車のハンドル部品成形に関するテーマです。
今はやや下火になった、局所補強の考え方を採用しています。
部分補強は補修の考えにも応用できる優れた設計思想である、
というのが個人的な考えです。
※関連コラム
コミングルをベースとしたCFRTPをE-bikeのフレームに適用
Revolin Sports Helix Pickleball Paddle / Revolin Sports INC. (USA)
亜麻(Flax)を組み合わせたピックルボール用ラケットです。
sweet spot(芯)の面積増加、打音の低下、耐久性の向上、
並びに二酸化炭素排出量削減を実現したと書かれています。
※関連コラム
まとめ
JEC World 2025概要とInnovation Award Finalistから見る近年の技術動向についてご紹介しました。
従来の軽量化だけを売りにした勢いは影を潜め、
耐腐食性を基軸としたFRP適用に関する考え方が広がってきたと感じます。
また個人的には不思議に感じていた炭素繊維崇拝文化も薄くなり、
FRPの主役といえるガラス繊維の話が増えてきたと感じます。
加えて熱可塑性樹脂に関する内容が厚くなってきたことも間違いなさそうです。
一方で既に述べた通り設計に関する情報は皆無で、
どうしても形を作るところだけに気持ちが向く雰囲気は、
そう簡単には変わらないのかもしれません。
FRPを本当の意味で使いこなせる企業や人が増えるのはまだ先だと思います。
ここ数年、個人的にはAAMの拡大によるFRP適用の事例が増えてくると感じます。
このような業界では設計知見は不可欠ですので、
今よりもう少し該当する情報が増えてくると期待しています。